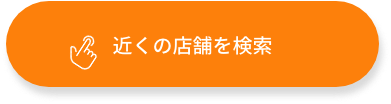在宅勤務を希望する際、ただ「家で働きたい」と伝えるだけでは、上司の納得は得られません。そのため、どのように伝えれば承認を得られるか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、申請理由の伝え方から、上司の不安を解消する具体的なアプローチ、信頼される業務報告の工夫まで、すぐに実践できるポイントをまとめました。育児・介護や体調不良など、状況に応じた例も紹介しているので、自分に合った伝え方の参考にしてください。
在宅勤務の申請理由として認められやすい例は?
在宅勤務を申請する際は、上司が納得しやすい理由を伝えることが重要です。以下は、その一例です。
・生産性を重視したい業務
資料作成や企画立案など、集中力が必要な作業に在宅勤務は適しています。オフィスでは電話や会話で中断されがちですが、自宅なら業務効率が向上します。
・天候不良で通勤できないのを回避できる
大雪や大雨の日は、出社に時間がかかったり、帰宅できなくなるリスクがあります。在宅勤務なら業務の遅れを防ぎ、無駄な残業も減らせます。
・外出・出張のある職種
直行直帰が可能になり、移動時間を報告書作成などにあてられます。交通費の削減にもつながります。
・人材採用の強化
在宅勤務可能と記載すれば、希望する応募者が増えます。まずは、自社で在宅勤務を実践する必要があります。
業務の効率化やコスト削減につながる理由を明確にすれば、承認される可能性が高まります。会社にとってメリットがある旨を伝え、納得を得られるよう工夫しましょう。
関連リンク:https://www.kaikatsu.jp/column/012443.html
通勤時間の短縮で業務効率が向上する理由
長時間の通勤は、体力と集中力が消耗し、仕事の質を下げる原因になります。通勤がなくなるだけで、気持ちに余裕が生まれ、1日の過ごし方に変化が現れます。
ITSUKI(東京都葛飾区)の調査では、在宅勤務の理由に「通勤時間の節約」を挙げた人が84.5%に上りました。片道1時間の通勤を省くと、月に約40時間が浮きます。節約した時間は、「休息」(52.2%)、「家事」(51.3%)、「趣味」(37.1%)に使うという調査結果が報告されています。
また、NTTグループのリモートワーク導入は、生産性向上の成功事例の一つです。NTTグループでは、リモートワーク環境の整備を行い、従業員の働き方を改革。転勤や単身赴任が不要になり、サテライトオフィスの拡充も進んでいます。
通勤時間の短縮は、従業員のワークライフバランスを向上させ、企業にも生産性向上やコスト削減につながるメリットがあります。
参照:在宅勤務を希望する理由、1位は「通勤時間の節約」空いた時間で何をする人が多いのか
育児・介護の具体的な両立プラン
育児や介護と仕事を両立するには、柔軟な勤務体制と職場の理解が不可欠です。2022年に改正された育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを育てる労働者や介護を担う労働者に対し、テレワークの導入が企業の努力義務として盛り込まれました。
実際に育児や介護と両立しながら働いている方の事例を3つ紹介します。
・育児と在宅勤務の事例
株式会社ディレクタスでは、育児・介護中の社員が出社回数を月1回まで減らせる制度を整備しました。社員のAさんは、リモート勤務により勤務時間を1時間延長し、朝の送りや夕方の家事に時間を割いています。勤務中は上司と相談しながらタスクを進めていき、育児と業務をバランス良く両立させています。
参照:仕事と子育ての両立 ~在宅勤務とチームワークの有難さ~
・①介護と在宅勤務の事例
介護のために働き方を変えた事例です。東京で仕事をしていたBさんは、要介護5の父親と過ごすために、実家のある静岡での在宅勤務に切り替えました。在宅勤務日である金曜は朝6時に勤務を開始し、15時半に業務を終了。午後は往診やケアマネとの面談に対応できるようスケジュールを組んでいます。
・②介護と在宅勤務の事例
突然の介護で退職を考えたが、在宅勤務に切り替えて復職を果たした事例です。Cさんは祖母の介護を理由に退職を希望。上司と話し合いを重ねた結果、一時的な休職を経て1日2時間の時短在宅ワークをスタートさせました。Slackでのこまめな質問や、タスクを手書きで可視化する工夫を通じて、社員とコミュニケーションを図り、仕事を進めています。
このように、育児や介護をするには、職場の理解を得たうえでの調整が欠かせません。上司と話し合い、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。
健康管理に基づく説得力のある申請理由
体調不良で無理に出社すると、免疫低下や症状の悪化につながる可能性があります。医学的にも、発熱や咳がある状態での通勤・勤務は回復が遅れる要因とされています。在宅勤務に切り替えれば、風邪気味でも体力の消耗を防ぎ、回復を早められるのがメリットです。
また、体調不良で出社すると、咳やくしゃみによって飛沫が広がる心配もあります。在宅勤務なら、周りへの感染も予防できるでしょう。
家族が体調を崩した場合も、自宅で看病しながら業務を継続でき、感染拡大を防ぐ手段としても有効です。回復の見込みや在宅勤務の終了時期を伝えることで、上司の理解も得やすくなります。
参照:国立保健医療科学医院|問1 熱や咳がある方については、どうしたらよいのでしょうか。
在宅勤務を上司に申請する際の効果的な伝え方
在宅勤務を申請する際は、上司が納得するような工夫が必要です。以下の手順に沿って準備しましょう。
・理由を具体的に整理する
育児・介護、健康、通院などの理由を明確にし、必要に応じて医師の診断書を添付します。
・会社へのメリットを添える
「作業に集中しやすくなる」「通勤負担がなくなることで報告資料の精度が上がる」など、実務へのよい影響を提示します。
・柔軟な勤務体制を提案する
「週3日は在宅」「会議や対面業務の日は出社」など、ハイブリッド型の働き方にすると承認されやすくなります。
申請書には、会社の方針に沿った形で在宅勤務することを明記しましょう。そのうえで、責任を持って業務にあたる姿勢を示すことがポイントです。
「緊急のときや対面が必要な場合は速やかに出社します」と、柔軟な対応が可能なのを明確にしてください。
上司の不安を解消する3つのアプローチ
在宅勤務を申請する際、上司が感じやすい不安に対する効果的なアプローチを紹介します。納得を得るためには、理由や対応策を具体的に伝えることが大切です。
やむを得ない理由なのか
上司は、在宅勤務が本当に必要なのかを確認したくなります。体調不良や家庭の事情など、やむを得ない事情を具体的に説明することが必要です。
たとえば、「体調が悪いのですが、締め切りが迫っているため完全に休むのは難しく、無理のない範囲で在宅勤務をしたい」と伝えると、仕事を続ける意思があることを示せます。
また、「子どもの通院に付き添うため、その前後は在宅で業務を進めたい」といった提案も、仕事と家庭のバランスを考えた理由です。
上司が「在宅勤務が必要な理由を詳しく教えてくれる?」と尋ねた際に、「家庭の事情で一時的に在宅が必要ですが、業務時間は確保できます。進捗は適宜報告します。」と伝えれば、納得してもらいやすくなります。
在宅だと生産性が下がるのではないか
上司は、「在宅だと作業が滞るのではないか」と不安に感じる場合があります。在宅でも集中できる環境を整えていると伝えましょう。
例えば、上司が「在宅だと業務が遅れないか心配だ」と言った場合、「締め切りまでに仕上げるため、集中しやすい環境で作業したいです。進捗状況はこまめに報告し、必要があればオンラインミーティングも設定します」と伝え、責任感と業務への意識の高さを示しましょう。
関連リンク:https://www.kaikatsu.jp/column/012444.html
在宅勤務をチームメンバーは了承しているのか
上司は、周囲との公平性や連携を心配する可能性があります。事前にメンバーと調整した内容を説明することが信頼につながります。
例えば、上司が「チームメンバーは在宅勤務をどう考えている?」と尋ねた際、「事前に相談し、進捗状況の共有を徹底することで問題ないと確認しました。緊急対応が必要な場合はすぐに連絡できる体制も整えています。」としっかり説明します。上司も、チームメンバーの了承を得ているのが伝わり、納得してもらえるでしょう。
数値で示す具体的な成果目標の立て方
在宅勤務では、成果が見えにくくなるため、目標を明確に設定し、業務を可視化する工夫が欠かせません。たとえば「週3件の商談設定」「月2件の提案提出」など数値化された目標が理想です。
業種別の企業の成果目標の具体例は以下のとおり。
・電気機器メーカー:職務記述書をもとに目標を設定し、成果で評価
・自動車部品メーカー:評価者研修を通じ、複数人で成果を確認する体制を整備
・情報・通信メーカー:ジョブ型制度により職務ごとの責任を明確にし、成果主義を徹底
進捗状況の報告は「前日実績・本日の目標・課題」の3点を定期的に共有すると説得力が増します。Slackや日報を使ってこまめに共有し、上司がフィードバックできる環境を整えましょう。
在宅勤務の申請でよくある質問と回答例
在宅勤務を申請する際、上司からいくつかの質問が出ることが予想されます。スムーズに承認を得るために、どんな質問がくるかを事前に考え、上司が納得できる回答を準備することが大切です。
以下で、上司から聞かれやすい質問とその回答例を紹介します。
質問:在宅勤務は、どのくらいの期間続ける?
回答例:家族が入院したため、2週間の在宅勤務を希望します。回復次第、通常通り出社します。
期間を明確に伝え、いつまで続けるのかを具体的に示しましょう。
質問:在宅勤務を希望する理由は?
回答例:親が体調不良で通院が必要な状態です。病院まで付き添いたいため、在宅勤務を希望します。
単に家で働きたいではなく、倫理的に納得されやすい理由を選びましょう。
質問:自宅で仕事はちゃんと進むのか?
回答例:仕事に集中できる静かな環境で作業します。朝に当日のタスクを共有し、夕方に進捗を報告します。
作業環境と進捗状況の報告を具体的に示すことで信頼感が高まります。
業務進捗の見える化と報告方法
在宅勤務では、仕事の進み具合を見える形で共有することが必要です。丁寧な報告が信頼につながるため、ExcelやWordなど扱いやすいツールを使って、業務の整理と報告を習慣化しましょう。
たとえばExcelでは、カレンダーのテンプレートを使うと、1週間の予定を簡単に管理できます。Wordでは、週ごとの業務記録をシンプルにまとめれば、振り返りにも役立ちます。
また、チャットツールを使ってテキストで日報を作成する場合は、以下のような項目を入れましょう。
・記入日
・部署
・氏名
・今週の目標
・主な業務内容
・課題・改善案
・コメント・所感
日報を書くときは、以下などの要素を整理して記録するのが、信頼を獲得できるポイントです。
・やったこと
・成果
・課題
・次の予定
書くことが決まっていると、毎週迷わずに記録でき、報告の精度も上がります。
業務が伝わるよう工夫した報告によって、在宅勤務中でも業務の見える化と報連相がスムーズになるでしょう。
在宅勤務を継続して認めてもらうコツ
在宅勤務を続けるには、上司の不安を取り除き、成果をはっきり見せることが大切です。まず、作業環境や報告ルール、勤務時間などをまとめた実施計画書を提出しましょう。
「朝9時から業務を開始し、12時・17時にSlackで進捗を報告します」など、細かく決めておくと信頼されやすくなります。「営業3件受注」「提案書を予定より2日早く納品」など、成果を数字で伝えると説得力が増します。
また、「週1で成果報告書を提出」「トラブル発生の際は30分以内に連絡」など、自主的なルールづくりもポイントです。過去の成果や専門スキルも簡潔にまとめ、自分が社内にどう貢献しているかを伝えると、在宅勤務の継続を認めてもらいやすくなるでしょう。
信頼関係を築く業務報告の書き方
在宅勤務では、進捗状況が伝わりづらいため、正確でわかりやすい業務報告が欠かせません。簡潔に読み手が内容をイメージできるように書きましょう。
たとえば、「資料作成」とだけ書くのではなく、「A社向けホームページリニューアル提案資料の構成案を作成」と記載すれば、具体的に伝わります。作業時間も「10:00〜11:30の間で作成」と書くと、より把握しやすくなります。
所感は「難しかった」などの感想だけで終わらせず、「構成に迷ったため、明日は営業担当とヒアリング内容を再確認する」といった対応まで含めましょう。
上司の信頼を得るために、誰が読んでも伝わるように書く意識が必要です。
在宅勤務をする上での注意点は?
在宅勤務は働きやすい点が魅力ですが、注意点やデメリットもあります。以下で、評価やコミュニケーション、情報管理など、注意すべきポイントを紹介します。
適切な評価を受けられない可能性がある
在宅勤務だと、働く姿が上司に伝わりづらいのがデメリットです。成果物だけで評価されると、それまでの努力や成長を理解してもらえない場合があります。その結果、同じ仕事ばかり任される、昇進の機会が減るといった影響が出るかもしれません。適切に評価されるためには、業務報告の中で過程や工夫も具体的に伝えましょう。
コミュニケーションが取りにくい
在宅勤務では、チャットやメールのやりとりが中心です。対面と違い、表情や声のトーンが伝わらないため、報・連・相がうまく伝わらない場合もあります。これを防ぐには、チャットでは結論から先に伝え、要点を箇条書きで整理するなど、文章構成にも工夫が必要です。
また、カジュアルミーティングを週1で設けると、心理的な距離が縮まり、ちょっとした相談もしやすくなります。
快適なネット環境なら快活CLUB
自宅ではネットが不安定だったり、集中できる場所がなかったりと、在宅勤務には意外と悩みがつきものです。そんなときにおすすめなのが、快活CLUBです。
全席にWi-Fiと電源があり、個室も使えるので、静かな環境で仕事に取り組めます。仕事が進まない日も快活CLUBなら、座り心地のよいチェアで快適に作業できます。
また、ドリンクバーや無料のモーニングがあるのもうれしいポイント。ちょっと気分を変えて仕事をしたい日にもぴったりです。
まとめ
在宅勤務を承認してもらうには、理由を明確に伝えたうえで、進捗状況の可視化や報告方法の工夫が必要です。上司が感じやすい不安は、事前に対応策を用意し、会社のメリットも伝えることで、承認の可能性が高まります。
自宅での作業が難しいときは、快適なネット環境と集中できるスペースがある快活CLUBを活用するのもひとつの方法です。自分に合った環境と働き方を見つけて、業務に取り組んでいきましょう。