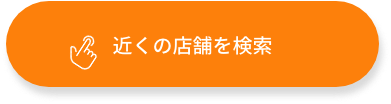大学生活にもだいぶ慣れてきた3年生になると、就活を意識し始める人も多いでしょう。実際に本格的に就活が始まるのは大学3年生の3月頃です。27卒・28卒の皆さんの中にも、そろそろ就活を意識して動き出そうと考えている方もいるかもしれませんね。
この記事では就活はいつから始めるべきか、就活のスケジュールを徹底解説します。企業別の選考時期と準備のポイントや就活でまずやるべきことなども紹介しています。
就活はいつから始めるのがベスト?徹底解説
就職活動を本格的に始める時期は大学3年生の3月頃と言われていますが、多くの学生は3年生の4〜6月頃から準備に入ります。この時期は企業のインターンシップの応募が始まるタイミングと重なることもあり、まずは業界研究や自己分析に取り組む人が多いようです。
理想的な就活開始時期はいつ?業界別の違いを解説
就活の開始時期は希望する業界によって異なります。業界ごとの選考開始時期は以下の通りです。
-
IT業界:大学3年生の10月ごろから
-
外資系コンサル:大学3年生の春ごろから
-
外資系金融:大学3年生の9月ごろから
-
外資系メーカー:大学3年生の9~12月ごろ
-
総合商社:3月1日から
-
マスコミ・テレビ業界:大学3年生の秋ごろから
このように、業界によって選考開始時期が異なるため、それに合わせて準備を進めなくてはなりません。特に早期選考を行うのは、総合商社や外資系コンサルなどです。近年、就活の早期化が強まっており、本選考よりも前にインターンシップを開催している企業の割合も増えています。そのため自己分析や業界研究、ガクチカなどの準備も余裕を持っておくことが肝心です。
就活の準備期間は選考開始の5か月前ごろから開始しておくと、余裕を持って準備ができます。例えば、3月に選考が始まるのであれば、前年の10月ごろから動き出さなくてはいけません。余裕を持って準備を進めることで、ほかの人と差をつけられるでしょう。
外部リンク:www.studyinjapan.go.jp/ja/work-in-japan/employment/schedule.html
就活準備に必要な期間はどのくらい?実態調査
就活に必要な準備期間は5か月程度ですが、その間には以下のことを行う必要があります
-
自己分析:自分の強みや弱み、価値観、興味関心などを分析し整理する
-
業界研究:興味のある業界や職種・企業の情報収集をして理解を深める
-
ガクチカ:学生時代に力を入れたことのエピソードを整理する
-
ES作成:企業に提出するエントリーシートを作成する
特に自己分析や業界研究は、一度きりではなく何度も行うことが大切です。特に業界研究は日々新しいトピックがあるため、5か月と言わずもっと前から行うのがベストです。
24卒の就活生は、3年生の夏から就活の準備をはじめ、インターンシップに参加しています。また、同じく24卒の就活生は、エントリーの半年前から準備をはじめ、適性検査や自己分析を行っていたようです。
どのように動けばいいかわからないときは、キャリアセンターを活用するのもおすすめです。
27卒の就活スケジュール完全ガイド
27卒の場合の就活の準備は大学3年の春から秋にかけて本格的に始まります。その間にインターンシップに積極的に参加する傍ら、自己分析や企業研究を積極的に進めていきましょう。前期と後期に分けて説明します。
3年生前期で得られるインターンシップ経験
3年生の前期は主に準備期間です。そしてインターンシップに参加して、企業で働いている人の話を聞いたり実際に業務を体験したりして、自分の将来像をイメージしていきます。
インターンシップで得られる具体的な経験は以下の3つです。
-
リアルな職業体験
-
社会人としてのマナーや素質
-
自己分析を深められる
インターンシップは短期と長期があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。限られた中でなるべくたくさんの業界を見たい場合は短期を選びましょう。業界をある程度絞れている場合は、長期を選べば具体的な業務を深く知ることができます。
リアルな職業体験をすることで業務の内容が具体的に分かり、自分に向いている仕事かどうかが分かります。また業務を通して自分の強みやスキル、専門性が明確になるため、就活先を絞るのに役立つでしょう。バイトとは異なる社会人としてのマナーを学べるのもインターンシップの特徴です。
3年生後期の具体的な準備ステップ
9月以降の3年生後期になると、すでに準備を進めている人とそうでない人で差が出始めます。3年の後期には次の準備を行いましょう。時系列で紹介します。
-
9・10・11月:秋インターンに参加、ESの準備、OB・OG訪問を進める
-
12・1・2月:冬インターンに参加、企業説明会に参加、面接対策、WEBテスト対策、早期選考に参加
9〜11月は、インターンに参加しながら、自己分析や企業研究をもとにしてエントリーシートを準備しましょう。前期の準備期間に多く情報収集して、自己分析をしている人は楽に進めることができますが、準備不足の場合はエントリシートが上手く書けず苦労します。直前で慌てないように春からしっかり準備を進めましょう。
12〜2月は、エントリーに向けた準備が本格化します。これまでの自己分析や企業分析を元にして面接対策を行いましょう。事前の情報収集をしっかりしておけば、企業説明会で内定後の自分の姿をイメージしやすくなるでしょう。
28卒の就活スケジュール完全ガイド
28卒でも1年後の就活を見据えて動き出しましょう。2年生のうちから就活に向けて準備を進めていけば、3年生になったときにより具体的なイメージを持って行動できます。ここからは28卒の就活スケジュールをガイドします。
2年生で築く就活基盤
2年生のうちから就活を見据えて動き出す場合は以下の3つの基盤を大切にしましょう。
-
自己分析や業界研究を始めておく
-
希望就職先に応じたスキルや資格を取得する
-
大学2年生でも利用できる就活サイトに登録する
自己分析や業界研究は、早いうちから進めておくことで就活が本格化したときに良いスタートが切れます。インターンシップなどに積極的に参加することで将来のビジョンが明確になるでしょう。
また、将来就きたい職種や業界がある程度決まっているときは、必要なスキルや資格を取得に向けて動きだしましょう。エンジニアを目指すのであればプログラミング言語の勉強や資格を取得に挑戦するのもおすすめです。
そして、大学2年生でも利用できる就活サイトに登録して情報収集をしましょう。キャリアに関する情報を早めにキャッチしておくことで、自己分析や業界研究に役立ちます。
3年生のインターン活用術
インターンシップは3年生になってからと考えがちですが、実は2年生からでもインターンシップに参加することができます。3年生になると、就活に向けてすべきことがたくさんあるため、2年生の余裕があるうちから参加した方が、視野を広げてスキルを身に着けることができます。
2年生がインターンシップに参加する時期は長期インターンや短期のサマーインターン、ウィンターインターンなどがあります。
実際に2年生でインターンシップに参加した学生は、早いうちからインターンシップに参加したことで業界や職種への理解が深まり、今後どのように行動したらよいかが明確になったようです。このように2年生からインターンシップに参加することで、余裕を持って就活を進めることができるでしょう。
企業別の選考時期と準備のポイント
前述の通り、選考開始時期は企業によって異なるため逆算して準備を進めましょう。大手企業の場合、倍率が高くなるため選考対策は必須。ほかの就活生と差をつけるためのポイントを紹介します。
大手企業の選考対策
大手企業の選考対策は、次の5ステップで行うと効果的です。
①企業研究:業界動向や企業理念を把握し、自分の志望動機に落とし込みます
②自己分析:自分の強み・弱み、価値観を整理し、エピソードと紐づけます
③ES対策:企業ごとの傾向を分析し、具体的な経験をもとに説得力のある内容にします
④面接対策:模擬面接で質問パターンに慣れ、論理的に話す練習を重ねます
⑤グループディスカッション対策:役割分担と発言のタイミングを意識し、協調性とリーダーシップのバランスを意識します
たとえば、企業研究が浅いと的外れな志望動機になってしまう可能性があります。そのため、1ステップずつ段階を踏んでいくことが大切です。
早期就活のメリット・デメリットとは?
企業が早期に内定を出す傾向が強まっている昨今では、早期に就活を始めざるを得なくなっています。早期選考に備えて早期から就活を始めるのにはメリットとデメリットがあります。よく理解した上で就活を進めていきましょう。
視野が広がる具体的な体験
早期から就活を始めることで、安心感を持って就活に臨めると感じている人が多いようです。確かに準備期間が長ければ長いほど、情報収集ができ企業の理解も深まります。長い期間で視野を広げて体験することで、本当に自分に合った職業を見つけることができるでしょう。
また2年生のうちからインターンシップに参加すれば、より多くの企業の業務内容を把握することができます。体験前後では、企業へのイメージも大きく変わることがありますし、これまで興味を持たなかった業界にシフトチェンジする可能性もあります。本当に自分に向いてる職業をじっくり吟味できるのも早期就活のメリットです。
学業との両立のリスク
早期就活をすると、タイミングによってはゼミが本格化するときと被ってしまい、学業と就活の両立ができなくなってしまう可能性があります。早く就活を終わらせて、のびのびとキャンパスライフを楽しみたいなどの目的で始めてしまうと、どちらも中途半端になってしまうこともあるため注意が必要です。
また早期就活は、知識が豊富になることで「もっと良い企業がある」と思い、就活が長期化する恐れもあります。就活が長期化すると、内定をもらっている周りと比較して良い就活ができません。
学業と就活をうまく両立するためには、事前に学業と就活両方のスケジュールを立てて、無理なスケジュールになっていないことを確認しましょう。
就活成功の第一歩!最初にやるべきこと
就活を成功させて希望先から内定をもらうためには、最初にどう動き始めるかが重要です。準備を始めたら特に「自己分析」と「業界研究」に力を入れましょう。それぞれを紹介します。
自己分析で見つける強み
面接や履歴書で必ずと言っていいほど聞かれるのが「自分の強み」です。面接官はこの質問を通して自社に遭った人材か、入社後に活躍する人材か、を見ています。
この自分の強みをアピールするために行うのが自己分析です。就活で必ず行う自己分析は、自分の特徴や長所・短所、価値観を把握・分析して自分の強みを見つけていきます。しっかりと自己分析をしておけば、回答に一貫性を持たせて志望動機の説得力を高めることができるでしょう。
自己分析の方法は「自分史」「モチベーショングラフ」「マインドマップ」「ジョハリの窓」などがあります。複数の診断ツールを使うと、より正確に自分の強みを把握できるでしょう。
業界研究での情報収集方法
業界研究の目的は、数多くある業界の種類や特徴を知って、自分が就きたい業界や職種を見つけるために行います。自己分析や企業研究と同じく、就活をする上でとても重要な作業です。
業界研究をするときは、さまざまな手段で多角的な視点を持つことが大切です。例えば以下の手段を活用しましょう。
-
就活情報サイト
-
新聞・ニュース
-
書籍・雑誌
就活情報サイトは大学1・2年生でも登録できるものもあります。企業の採用情報はもちろん、業界の詳細やセミナー・イベントの案内など、就活で必要なコンテンツが網羅されています。
また新聞やニュースで業界の最新情報を入手しましょう。事業展開や業績、景気や円相場などに注目することで、各業界の動向を把握しましょう。書籍や雑誌も、業界全体の動きや全体像の把握に役立ちます。
内定獲得へ!効率的なスケジュール管理法
内定を多く獲得して、自分が希望する企業に就職するためには、数多くの企業にエントリーしなくてはなりません。エントリー先が多くなると予定を把握できなくなるため、ツールを活用してスケジュールを管理しましょう。
選考状況の見える化テクニック
複数の企業にエントリーするときは就活スケジュールや選考状況の可視化は必須と言えるでしょう。おすすめの管理方法は以下の4つです。
-
エクセルで自作のシートを作る
-
スケジュール帳
-
Googleカレンダー
-
スケジュールアプリ
このように、ツールやアプリを使ってスケジュールを把握しておくと、優先順位を明確にしてタスクを確実に実行できるようになります。スケジュール管理のコツは、タスクを終結させて優先順位を決めて優先順位の高いタスクから必要な時間を見積もって逆算して取り組むことです。
複数の企業を受けるときは、企業ごとに色分けをしておくとより分かりやすくなります。リマインド機能などを使いながら効率よく就活を進めていきましょう。
快活CLUBで就活!
就活中は24時間365日利用できる快活CLUBを使ってみませんか?快活CLUBは、30分単位で利用できるため、インターンシップ前やエントリーシートを作成するとき、自己分析や企業分析で集中して取り組みたいときなどさまざまな用途で利用できます。個室完備のため、周りを気にすることなく取り組めますよ。ぜひお近くの店舗をご利用ください。
まとめ
優秀な人材を早いうちから確保したいと、多くの企業は早期から選考を行うようになっています。それに伴う就活生は大学2年生などの早いうちから動き出す人も多いです。
就活で大切なのは、スケジュールを管理してしっかりと準備を進めていくこと。特に自己分析や業界研究は時間をかけておくと、面接の際に強みをアピールしやすくなります。本記事を参考に効率よく就活を進めましょう。